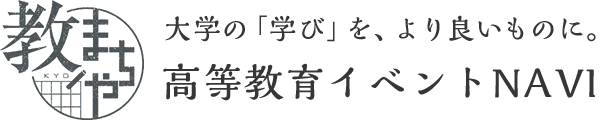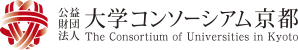「スタッフレポート」15:京都薬科大学「薬用植物園御陵園 初夏の一般公開」
■万葉の時代に渡来したアカヤジオウなど、薬用植物の初夏の姿を初公開
こんにちは。教まちや事務局です。
大学コンソーシアム京都加盟校の職員の方にリレー形式でレポートをしていただく「スタッフレポート」京都薬科大学編です。
それでは夜船(よぶね)さんよろしくお願いします!
佛教大学の冨永さんよりバトンを受け取りました、京都薬科大学 会計課の夜船と申します。
今回のスタッフレポートでは、本学が2019年5月25日(土)に初夏のシーズンでは初めて実施した、本学附属薬用植物園御陵園の一般公開について紹介します。
■本学薬用植物園について
本学は薬用植物園として、本園(京都市伏見区、約13,000 ㎡)と御陵園を設置しています。
御陵園は、京都市山科区の本学本校地に程近い場所に、学生が薬用植物について学ぶための見本園として2012年に設置されました。面積約2,700㎡の敷地には畑や熱帯植物を栽培する温室、水生植物を栽培する池、庭園があります。園内にはボタンなど生薬の基原となる様々な薬用植物約300種を植栽しており、それらの形態的特徴や利用部位を学生が観察する実習などを行っています。

 2014年からは毎年秋に公開講座のプログラムとして見学会を開催し、普段よく目にする植物や果物が生活のなかでどのように生薬として用いられているのか等、地域の方々に薬用植物に関する知識を広く普及・啓発するための活動を実施していますが、来場者の方々からの「春に花の咲く薬用植物も観賞したい。」との要望にお応えし、2019年は初夏にも、そのシーズンに見ごろとなる薬用植物約30種類の開花に合わせて一般公開を行い、秋季とは趣の異なる園内をご覧いただきました。
2014年からは毎年秋に公開講座のプログラムとして見学会を開催し、普段よく目にする植物や果物が生活のなかでどのように生薬として用いられているのか等、地域の方々に薬用植物に関する知識を広く普及・啓発するための活動を実施していますが、来場者の方々からの「春に花の咲く薬用植物も観賞したい。」との要望にお応えし、2019年は初夏にも、そのシーズンに見ごろとなる薬用植物約30種類の開花に合わせて一般公開を行い、秋季とは趣の異なる園内をご覧いただきました。
■初夏の御陵園で見られる薬用植物の一例
アカヤジオウ(赤矢地黄)

※写真は近縁種のカイケイジオウ(懐慶地黄)
日本最古の歌集である「万葉集」が編纂された時代に中国から渡来したとされています。
6~7月頃に美しい紅紫色の筒状の花が咲きます。根は、滋陰(体を潤す)・清熱(不要な熱を取り除く)作用などを目的に生薬(地黄)として用いられます。
トウキ(当帰)

6~8月頃にかけて白い小花をつけます。根は、補血(血の不足を補う)・強壮作用などを目的に生薬(当帰)として用いられます。また、葉はセロリのような香りがあり、入浴剤などに用いられています。
■学生スタッフが薬用植物を解説
植物園内では見学エリアごとに、本学の学生が教員とともに薬用植物の特徴や効能を解説するスタッフとして参加し、来場者の方々への解説と質疑応答を行いました。
本学の学生は薬学部ということもあり、卒業後は病院や薬局の薬剤師となることを目指す学生が多いですが、薬学の知識があまりない一般の方々に対して、在学中に薬剤に関するコミュニケーションをとれる機会は多くありません。今回の一般公開は、地域の方々への薬用植物知識の普及・啓発に貢献するだけではなく、学生自身が将来、医療人として薬学の知識を正しく説明するための経験と、薬用植物の知識を整理する貴重な機会となったことと思います。


■おわりに
公開日当日は猛暑日の予報にもかかわらず、本学の想定を超える多数の方にご参加いただくことができました。
また、来場者の方々からは多くの高評価をいただくことができましたので、次年度以降も開催できるよう努め、地域に貢献していきたいと考えています。